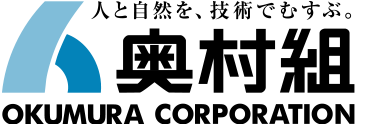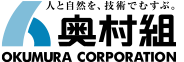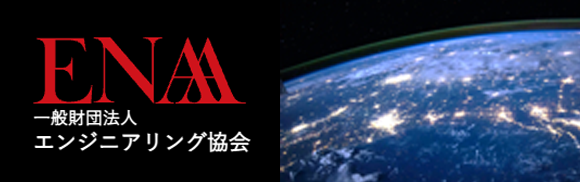トップメッセージ
トップメッセージ

「変わらない信念」と
「変えていく勇気」を持って、
さらなる成長を目指します

「変わらない信念」と「変えていく勇気」
経営者は「変えてはいけないこと」「変えなければならないこと」をしっかりと見極め、時代の流れに即した経営を行わなければなりません。「変わらない信念」「変えていく勇気」。この二つを持ち合わせることが、会社の持続的な発展につながっていくと考えています。
「変わらない信念」として奥村組に脈々と引き継がれる「堅実経営」「誠実施工」。これは奥村組創業者で私の曽祖父でもある奥村太平が、会社経営における心得として大切にしていたものです。奥村家は代々、農業を営んできた家系でしたが、太平が生まれた頃は機織物業を家業としていました。太平の祖父や父は豪快な人物で気前が良かった反面お金の管理には疎く、機織物業の経営は次第に逼迫します。そうした中、太平は若くして家業を任されますが、多額の債務で経営は如何ともしがたく、債務返済のために田畑など家産のほとんどを処分することとなります。こうした苦い経験から、太平は会社経営においても私生活においても終生「堅実」であることを貫いたそうです。機織物業を整理した後、太平は地方公務員を経て、建設業の道に進みます。誠心誠意を生涯の旨とした太平の「誠実」な仕事ぶりが、周囲からの信頼を勝ち得て、今に続く奥村組の礎を築きました。私で奥村組社長は5代目となりますが、太平の時代から奥村組の本質として脈々と受け継がれてきた「堅実経営」と「誠実施工」は、これから先も「変わらない信念」であります。
一方で、変えなければならないこともあります。建設業は今、将来の担い手不足や時間外労働の罰則付き上限規制への対応など、従前のやり方のままでは乗り越えることができないであろう課題を抱えています。当社は業務改革推進プロジェクトを立ち上げてICTの活用等により仕事の進め方を抜本的に見直すほか、TVCMなどを活用した積極的な広報活動により建設業や当社の魅力を発信、さらには、産官学民の連携により新技術の開発や新規事業への参入を目指す拠点「クロスイノベ―ションセンター」を新設するなど、時代に即した新たな奥村組へと変化を続けています。
「変わらない信念」と「変えていく勇気」を持って、奥村組はさらなる成長を目指します。
「現場力」に磨きをかける
中期経営計画(以下、中計)の2年目となる2023年度は、売上高が前期比15.5%増の2,881億円、営業利益は15.7%増の137億円となりました(【中期経営計画】)。
売上高については、中計目標の2,800億円を前倒しで達成することができましたが、利益目標達成にはもうひと踏ん張り必要な状況です。土木事業については、インフラの老朽化にともなう維持管理・更新需要に加え、社会資本整備のための公共事業投資が底堅く推移したこと、建築事業についても、新型コロナウイルス感染症の5類への移行を背景に企業の設備投資が回復基調を辿ったことなどから、計画を超える受注高を確保できましたし、今年度期初の繰越工事高も進行基準の全面適用(2009年度)以降では最も多く、手持工事が十分に積みあがっている状況です。
建設投資は引き続き堅調に推移し、恵まれた受注環境が続くと見込まれますが、資機材価格の高騰や2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の罰則付き上限規制の影響による建設コストの上昇は、利益を圧迫する大きな懸念材料となっています。選別受注を徹底するとともに、工事を手戻りなくスムーズに進めて高品質な土木構造物、建築物をお客さまにお納めしつつ、しっかりと利益も確保できるよう全力を尽くしていかなければなりません。とりわけ「生産性の向上」は建設業における喫緊の課題であり、当社もICT技術の積極的活用やDX推進等による業務改革を強力に推進しているところですが、あわせて、これまでお客さまからご評価いただいてきた、当社の強みである高い「現場力」を維持、向上させていくことも非常に重要であると考えています。単品受注現地生産でモノづくりをする建設業における「現場力」とは、まずは“設計図書を読み込み理解して現場がどうあるべきかを思い描く力”、次に“現地現物を自分の目で確認して現場がどうなっているかを把握する力”、さらには“現場に関わる全ての関係者と的確なコミュニケーションをとりながら計画的に仕事を進め、現場をあるべき姿に導く力”だと考えています。
当社は、施工管理にあたって、職員が現場に張り付いている時間が他社に比べて長いと言われます。ゼネコン職員は協力会社への作業指示と管理に徹するべきか、現場で一緒になって汗をかきながら進めるべきか、昔から議論があるところですが、私はゼネコン職員もできる限り現場に密着し、協力会社の作業員さんと密なコミュニケーションを図りながら施工にあたるべきだと思っています。現場のリアルな状況をしっかりと把握することで、トラブルの芽を摘み取る力、トラブルが発生しても早期に適切に対応する力が養われるはずです。しかしながら、昨年度に安全・品質面でのトラブルが何件も発生したことは「現場力」が低下していると言わざるをえず、残念でなりません。人手不足の問題もあって、現場勤務の職員は施工管理の本質的な業務(コア業務)だけでなく、さまざまな書類の作成など、多岐にわたる業務に忙殺されています。この現状を変えるべく、本年4月に現場を支援する内勤部署を新設し、現場勤務の職員がコア業務に専念できる体制を構築しました(【特集2】)。
新設部署には技術面の教育機能も持たせ、若手職員が早期に「現場力」を培うことができるようにしています。
変わらない信念である「誠実施工」を体現する「現場力」にさらに磨きをかけ、中計の基本方針に掲げる「企業価値の向上」にもつなげていきたいと考えています。
人を大切にする会社
当社のシンボルマークは漢字の「人」をモチーフにしています。これは、「人を大切にする会社」であることをあらわしたものです(【ロゴマークの由来】)。当社は、株主さま、お客さま、協力会社、地域住民の方々など、全てのステークホルダーを大切にするべき「人」と捉えています。
まず、株主の皆さまには、株価の向上と着実な配当でご期待に応えなければなりません。近年は、業績が堅調に推移したことなどから株価は右肩上がりに上昇してきましたし、配当についても業界トップクラスとなる “連結配当性向70パーセント以上” を株主還元方針としています。2023年度には、中間配当金77円、期末配当金160円の1株当たり237円と、前期比で14円増配することができました(【財務戦略】)。
そして、「企業は人なり」と言われるように、社員も大切にしなければならない「人」ですので、中計の基本方針に「人的資源の活用」を掲げ、さまざまな取り組みを進めています。「働き方改革」のアクションプラン「OKUMURA LIFE WORK PLAN 2024」を定め、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた社内制度の拡充や、多様な人材がより活躍できる環境の整備、工事所の4週8閉所の実現を目指した施策などを着実に実行しています。また、女性の活躍推進については、ダイバーシティ経営などに関する豊富な知識をお持ちの社外取締役 上田理恵子氏にお力添えをいただきながら取り組んできた結果、2023年度の「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰において「優秀賞(大規模企業部門)」に選出されたほか、「えるぼし認定」の最高位を取得することができました(【女性活躍推進への取り組み】)。
「攻めの広報」で人材確保
数年前、ある民間建築の案件で、見積金額は当社が一番低かったにもかかわらず、お客さまが当社のことをあまりご存じなかったために、競合他社へ発注されてしまうということがあり、なんとも悔しい思いをしました。また、知名度の低さが新卒採用活動においても大きなマイナス要因となっていて、毎年苦戦を強いられていました。そうしたことがあって、それまでトラブルが発生した際のマスコミ対応などを主なミッションとしていた広報部門に、知名度や好感度の獲得を目的とした積極的な広報活動を展開するよう指示し、「守りの広報」から「攻めの広報」へと大きく舵を切りました。
この「攻めの広報」の柱となっているのが、2018年に初めて制作したTVCMです。女優の森川葵さんに当社の建築職員“奥村くみ”役を演じていただいている「建設LOVE 奥村くみ」シリーズは、手前味噌ながら大変好評で当社の知名度や好感度を大きく引き上げてくれていると感じています。新規のお客さまの中にも当社のCMをご覧いただいている方は多く、営業活動がしやすくなりましたし、新卒採用においても多くの優秀な学生が当社を志望してくれるようになり、目標採用人数の確保につながっています。私はTVCMを制作するにあたって広報部門に二つの注文をつけました。一つ目は、建設業界全体のイメージを向上させるものにすること。これは建設業の仕事に魅力を感じる人が増えなければ、将来の担い手確保が難しくなり、建設業界の衰退を招くと考えるからです。最新作の「新3K+K」篇と「KAKKOII(カッコイイ)」篇も、まさに建設業のイメージアップを狙ったものとなっています。そして二つ目は、大阪本社の企業らしく“クスっと笑える”ものにすること。これは、他社との差別化を狙ったもので、CMの最後には必ずオチをつくっています。当社HPのCMギャラリーで是非ご覧ください。
明日へ向かって挑戦を続ける
中計に掲げる「技術優位性の向上」や「新規事業の拡大」は、産官学民の技術者やベンチャー企業の経営者などと交流・連携することで、自社だけで取り組むよりも大きな成果が得られると考え、2023年10月、東京丸の内に新オフィス「クロスイノベーションセンター」を開設しました(【クロスイノベーションセンターHP】、【特集1】)。
建設事業において当社の看板となるような技術の開発、環境問題や食料問題、少子化問題といった社会課題の解決への貢献も意識した新規事業への参入(【投資開発事業等】)を進めている中、この新拠点で社内外のさまざまなリソースを活用したオープンイノベーションを強力に推進し、その取り組みをさらに加速させていきます。
海外事業については、台湾とシンガポールで土木事業を中心に展開しています。台湾には2001年に進出したのですが、通じない言葉、信頼できる協力会社の不在、異なる商習慣など、国外での工事特有の難しさに直面し、なかなか事業を軌道に乗せることができませんでした。非常に苦しい時期が長く続きましたが、当社が得意とするシールド工事に特化したことなどが奏功し、ここに来てようやく利益面でも業績に寄与するようになりました。異国の地でも貫いた「誠実施工」が高く評価され、数々のシールド工事案件を受注しています(【特集3】)。今後、シンガポールにおいても強固な事業基盤を構築できるよう全力を尽くす所存です。
最後に

139名の新入社員を4月に迎え、心新たに2024年度のスタートを切りました。下記に示す方針のもと、「2030年に向けたビジョン」の実現を目指し、今年度も全社全力で邁進していく所存です(【2030年に向けたビジョン】)。引き続き、皆さまのご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
- 社長方針
-
経営理念のもと、社会の持続的な発展に貢献するために、社会のニーズの変化を見据えた事業・サービスを展開するとともに、ESG/SDGsに関わる取り組みを一体的に推進し、確かな技術と誠実な事業運営により社会の信頼に応え、成長し続ける企業グループを目指す。
そのビジョンの実現に向け策定した中期経営計画の目標達成のために、次の活動を推進する。- 1. コンプライアンスの面では、法令順守の徹底を図るとともに、企業行動規範のもと、企業倫理に則った事業活動を推進する。
- 2. 安全衛生面では、進捗第一になりかねない施工を排し、「真の安全第一」を追求し、労働災害の撲滅を図るとともに、快適な職場環境を形成する。
- 3. 品質面では「顧客満足」「社会的信頼」の向上を目指し、品質管理を徹底するとともに、顧客のニーズに即した製品、技術、サービスを提供する。
- 4. 環境面では「人と地球に優しい環境の創造と保全」を目指し、環境汚染の予防、環境負荷の低減および環境の保全に取り組む。
- 5. 労働環境面では、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、働き方改革の推進および心身の健康の保持増進を図る。
- 6. 統合マネジメントシステムの適確な運用ならびに継続的な改善により、事業活動にともなうリスクを管理し、業務を効果的かつ効率的に遂行する。
全役職員は、この方針に基づき、自らの果たすべき職務あるいは責任に即した目標を設定し、主体性をもって達成に向けて取り組む。